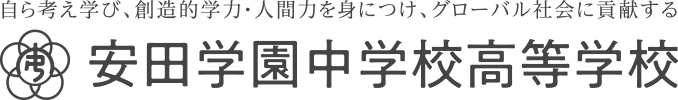探究プログラム
- TOP
- 中学校を受験される方へ
- 探究プログラム
“根拠”と“論理”の意識を高め、思考力・表現力・創造力を生み出す
「探究」の授業では、個人やグループで気づいた疑問を〔観察→疑問→仮説→検証→考察〕などの方法により根拠をもって論理的に探究することを学びます。
この探究を議論や発表を経て行うことが、自ら考え学ぶ行動そのものであり、コミュニケーション力の育成、多角的に考えるきっかけにもなります。
探究を通じて育成した思考力が、今後、最難関大学を突破する力となり、さらには社会に出た後も活かせる能力となっていきます。

各学年の到達目標
1年生 |
プログラム |
「自然科学探究」 |
テーマ |
●自然(動物)を探究する |
|
2年生 |
プログラム |
「社会科学探究」 |
テーマ |
●ビオトープ作りを通して、自然と人間との関わりについて考える |
|
3年生 |
プログラム |
「地域研究」 |
テーマ |
●課題を発見・解決する話し合いを実践する |
|
4年生 |
プログラム |
「個人探究」 |
テーマ |
●これまでに培った個人の探究力を活かす |
|
5年生 |
プログラム |
「個人探究の応用」 |
テーマ |
●グローバルコミュニケーションを体験、主体的な国際的視野を育てる |
ディベート授業

批判的思考力(critical thinking)、論理的思考力(logical thinking)、迅速な思考力(quick thinking)といった能力を養成する目的で、3年次の社会科の授業で実施しています。相互的なコミュニケーションで、これらの思考力を発揮する前提となる傾聴力や、説得的に伝える発信力も鍛えられます。

自然科学探究ー磯で生き物さがしー(1年生)
通常の授業では体験できない自然(磯)観察を通し、新たな気づき・発見から興味・関心を広げ、探究力・思考力の向上を図ります。まず磯全体を観察し、どんな生物がいるか、興味・関心を持った生物を観察し海から採集、採集した生物について班で意見を出し合います。探究する生物を決定し観察、その後観察した内容をまとめ疑問・仮説を考え観察・実験・検証を行います。

自然科学探究ー一番飛ぶ飛行機選手権ー(1年生)
自然科学の探究は〔観察→疑問→仮説→検証→考察〕の5つの段階があります。探究は、この5つの段階を何度も繰り返し、試行錯誤することにより深めることができます。1年生の2学期には「一番飛ぶ飛行機選手権」を開催し、自分たちが作った飛行機にどのような工夫をほどこしたらより飛ぶようになるか仮説を立て、検証を繰り返すことにより探究的な思考力を高めていきます。

社会科学探究ー新潟県十日町市でトキ研究ー(2年生)
2年生では、「新潟県十日町市にトキを放鳥したら野生に定着するか」という疑問に挑みます。1学期にトキについて深く調べ、夏の宿泊行事で新潟県十日町市に行き、さまざまな調査を行います。調査結果を持ち帰り、疑問に対する自分たちの意見をまとめていき安田祭で発表を行います。この過程で自然科学と社会がどのようにつながっているかや情報収集やデータ処理の方法を身につけていきます。
地域研究(3年生)
「地域の歴史や文化を研究調査する」、「自然と人間生活について考える」が地域研究の目的となります。事前学習ではさまざまな情報収集を行い、グループごとでテーマを決めて仮説を立てて、現地で何を調査するかを決めます。自分たちのテーマを検証するためにどのように行動したらよいかを自分たちで考え、計画を立てることが地域研究の重要なポイントです。
個人探究(4・5年生)
1~3年生までに学んだ探究力を活用し、各自の興味・関心に合わせた探究を行います。ゼミ形式を採用し、専門的な探究を実践します。ゼミでは担当の先生からアドバイスを受けながら、個人で探究し、その成果を発表するだけではなく、論文にまとめます。